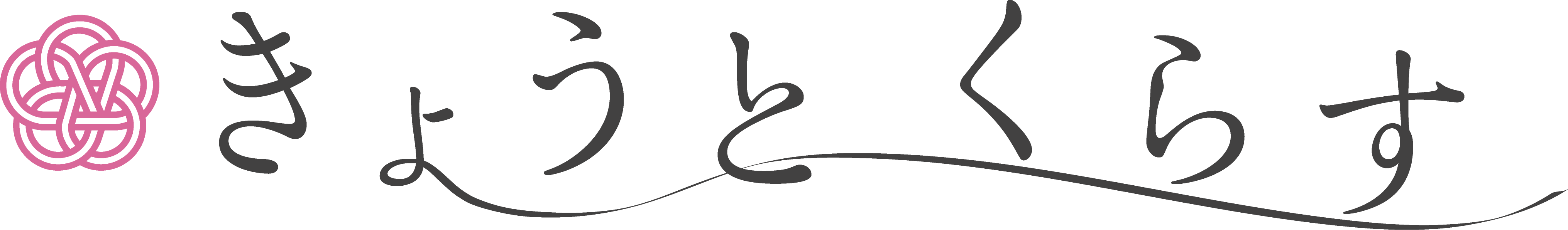2024年で開園100周年を迎えた京都府立植物園。
日本で最初の公立の植物園として誕生して以来、府民に親しまれ、歴史を重ねてきました。四季折々の草花の栽培はもちろん、希少な植物の保全にも力を入れています。
このコラムでは、植物の専門家である戸部園長に季節ごとの見どころやユニークな植物の生態を教えてもらいます。物言わぬ植物から学ぶことはたくさん!緑に癒され、潤いある暮らしのヒントも見つけてくださいね。

11月が見頃の植物たち
多くの日本の植物は、年に2度、春と秋に細胞分裂をします。暑い夏と寒い冬の間は細胞分裂をお休みする傾向にあります。つまり植物は、春先と秋の初めの2度枝や葉や花芽が成長します。春、植物園のバラは5月に一斉に開花し見ごろを迎えます。

見ごろを終えた夏にバラの枝を剪定すると、9月、10月に新しい枝が伸びて秋深まる11月には再び花を咲かせます。今年の夏は長く、暑さも厳しかったですね。そのため枝の剪定も遅めに行われ、花の見ごろも例年よりも少し遅れています。それでもバラは年に2回も花を楽しませてくれる優れものです。


現在植物園には、320種1400株が栽培されています。植物園は、かつて戦後にその敷地を連合軍の住宅地と利用されました。
返還されてから1961年に再開園するまでの準備期間と合わせて15年もの空白期間がありました。実は再開園したときには、植物園内にバラはありませんでした。その数年後にバラが導入されたようです。そのときの株の多くが60年以上も経った現在まで生き残っていると考えられます。
さて、実は今ばら園で咲いているバラのほとんどは自然界には存在せず、かつて人間が作り出した園芸植物なのです。1867年にフランス・リヨンの育種家が発表したラ・フランスは交雑種第1号でした。

(ラ・フランス)
まだ遺伝子もDNAも発見されていなかった時代、異なる種を交配するとこれまで見たことがないバラが生まれることを知ったのでしょう。ラ・フランスは、コウシンバラという中国原産の野生バラを元にして作ったといわれていますが、今はその由来ははっきりとはしていません。

(コウシンバラ)
園芸バラがつくられる元になった野生バラは8~10種あり、それらは全てアジア産です。日本でも知られるテリハノイバラやハマナスも含まれます。ちなみに、先日植物園を訪れた皇后陛下のお印は、ハマナスです。

(テリハノイバラ)

(ハマナス)
バラ(属)を含む植物群をバラ科といいます。バラ属150~200種を含む全体で2800種を超えるやや大きな植物群です。そんなバラ科の花の基本形は5数性です。ふつう外側から萼片5枚、花弁5枚、雄しべ20本(5本ずつ4輪、ただし一番外側の5本はそれぞれ2本に分枝)、雌しべ多数をもっています。
野生バラの花も基本形はバラ科のそれに一致しますが、雄しべがさらに枝分かれして合計30~100本以上の数になっています。さらに、野生ばらの花弁は5枚ですが、園芸バラは5枚以上の花弁があり、外側の雄しべが花弁に変態化したものです。そんな豆知識とともにバラを鑑賞してみて下さい。
11月、秋も深まるなか、園内には「貴船菊(シュウメイギク八重咲)・常緑ヤマボウシの果実・ホトトギス・クニフォフィア クリスマスチアー」などの植物も楽しむことができます。
戸部 博 京都府立植物園 園長
1948年青森生まれ。東北大学理学部卒業。千葉大学理学部助手、京都大学理学研究科教授など39年間大学につとめる。その後、日本植物分類学会長、日本植物学会会長などをつとめ、2018年4月1日より京都府立植物園の園長に就任。自らの主導により植物や植物多様性保全、京都府立植物園に関する研究を専門家によって一般の方に分かりやすく伝えるサイエンスレクチャーを2023年より植物園にて開始。
文/戸部 博
【画像】京都府立植物園