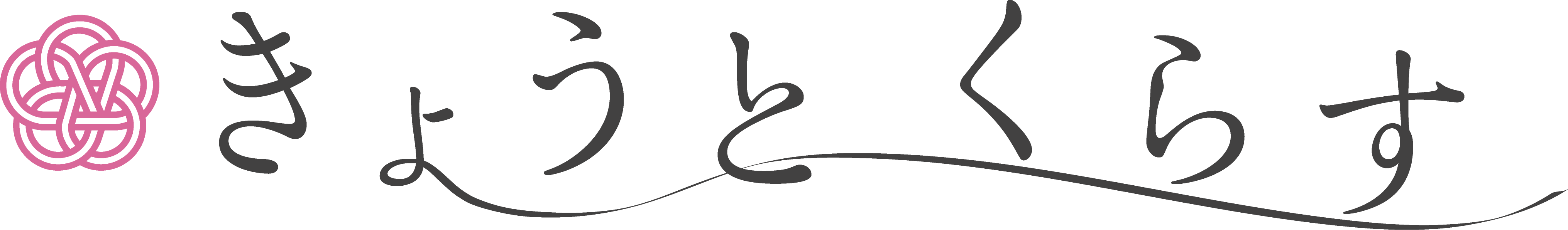2024年で開園100周年を迎えた京都府立植物園。
日本で最初の公立の植物園として誕生して以来、府民に親しまれ、歴史を重ねてきました。四季折々の草花の栽培はもちろん、希少な植物の保全にも力を入れています。
このコラムでは、植物の専門家である戸部園長に季節ごとの見どころやユニークな植物の生態を教えてもらいます。物言わぬ植物から学ぶことはたくさん!緑に癒され、潤いある暮らしのヒントも見つけてくださいね。

9月が見頃の植物たち
毎日暑い日が続いています。そんな中、太陽と青空にカンナの花がよく映えます。

カンナは、単子葉植物のカンナ科という僅か10種だけからなる小さな科の1種とその園芸品です。
種のほとんどが南米に生息していますが、カンナだけは原産地が南米から北米南部まで広がっています。さらにカンナは、アジアやアフリカにも運ばれています。1753年には、リンネ(学名の命名法の創始者)がインドで見つけたカンナの株に「Canna indica L.」という学名をつけています。カンナという名前は学名を呼んだものです。
カンナの花をよく見たことはありますか?正面からみて、カンナの花ほど不細工な花はありません。
花の左右が不釣り合いで、花弁に見えるもの不揃いで、しかも花全体が曲がっています。
もともとカンナの花は、他の単子葉植物の花と同じように、基本的に3数性です。つまり、萼片・花弁・雄しべ・雌しべが、3またはその倍数の6が基本になった花をもっています。実際に1個のカンナの花を開いてみてみましょう。


一番外側に、3枚の萼片が合着して小さな壺のようになっています(その下に子房があります)。次に、細長いひも状の3枚の花弁があります。さらにその内側に、6本(外側に3本、内側に3本)の雄しべがあり、これが全て赤やオレンジ色の花弁状に広がっています。写真では、外側の3本の雄しべのうち2本(枚)は合着しています。最後に雌しべが1本あります。雌しべの子房は3つの部屋(袋)に別れていて、3心皮(心皮は子房をつくる基本単位、1部屋が1心皮に相当します)からできています。こんな風に、カンナの花は一応3数性の基本形を保っています。
ところが、カンナの花では、花弁状に広がった6本の雄しべが全てかたちが不揃いで、しかもそのうち5本は全く花粉をつくりません。

残り1本だけが、しかも雄しべの片側の葯(花粉をつくる袋)だけしか発達しません。つくられた花粉は、いったん近くの雌しべに運ばれて、その壁にべたりと付着します。

花の奥深く、子房の上部には蜜が沁みだしているため、雌しべの壁の花粉は、蜜を吸いにきた送粉者(鳥かチョウ)のからだについて運ばれます。このような花粉の散布様式を二次的花粉放出といい、ユニークな花粉運搬様式の1つとして知られています。
ついでに、カンナでは、左右が違うかたちは花だけではありません。葉もまた左右が非相称です。カンナと似たような不細工な花と二次的花粉放出は、カンナ科に最も近縁なクズウコン科の花でも見られます。温室内に6月ごろ花が咲きます。いつか見てみてください。 他に、夏から秋へ、植物園では、レンゲショウマや熱帯スイレン等が見られます。

(熱帯スイレン)
戸部 博 京都府立植物園 園長
1948年青森生まれ。東北大学理学部卒業。千葉大学理学部助手、京都大学理学研究科教授など39年間大学につとめる。その後、日本植物分類学会長、日本植物学会会長などをつとめ、2018年4月1日より京都府立植物園の園長に就任。自らの主導により植物や植物多様性保全、京都府立植物園に関する研究を専門家によって一般の方に分かりやすく伝えるサイエンスレクチャーを2023年より植物園にて開始。
文/戸部 博
【画像】京都府立植物園