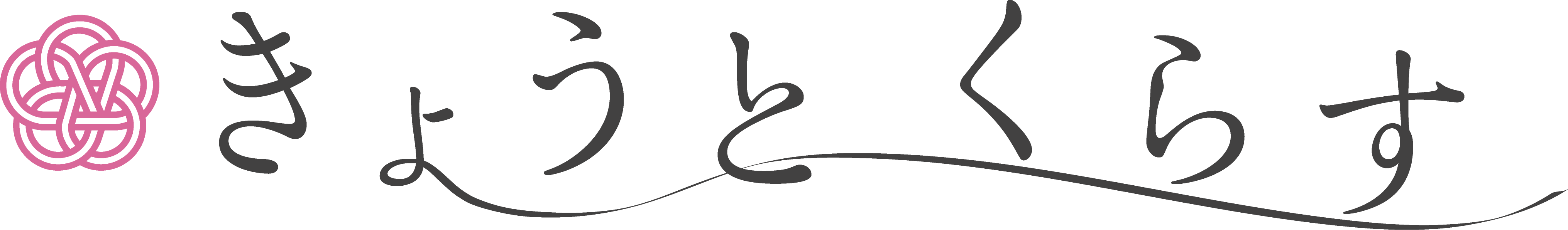2024年で開園100周年を迎えた京都府立植物園。
日本で最初の公立の植物園として誕生して以来、府民に親しまれ、歴史を重ねてきました。四季折々の草花の栽培はもちろん、希少な植物の保全にも力を入れています。
このコラムでは、植物の専門家である戸部園長に季節ごとの見どころやユニークな植物の生態を教えてもらいます。物言わぬ植物から学ぶことはたくさん!緑に癒され、潤いある暮らしのヒントも見つけてくださいね。

10月が見頃の植物たち
みんな大好きなチョコレート。チョコレートの原材料となる植物が有用植物室に1本植えられています。1753年、リンネがその植物に「植物の種」という本の中で、「Theobroma cacao 」と命名しました。
「Theobroma」はギリシャ語で神様の食べ物、cacaoは16世紀にメキシコ中央高原に栄えたアステカ文明の言語に由来する「苦い水」を意味しています。これだけでチョコレートっぽいですね。原産地は南米北部ですが、現在は中南米のほか、アフリカ、中国にも運ばれて栽培されています。植物園では、8月ごろから11月にかけて、小さな白い花が次々に開花します。

幹生花といい、新たに伸びた枝からではなく、古い太い幹から毎年花が咲きます。多くの植物では、花があればその下方に必ず葉があります。しかし、カカオの花は葉がないところに咲きだすので、とりわけ目立ちます。

カカオは、ムクゲなどと同じアオイ科の1種で、その花は5数性です。直径はおよそ7~8ミリ、外側から順に萼片5枚、花弁5枚、雄しべ5本、(花粉をつくらない針状の)仮雄しべ5本、(5心皮からなる)雌しべ1本があります。

花弁のかたちが変わっていて、その中央部が外側に袋状に湾曲し、その先の長く伸びたところが黄色く色づいています。

実は、袋状の花弁の湾曲部に雄しべの葯が隠されています。

このように、自家受粉ができないような花の構造になっています。 ただし、自分の花の雄しべの花粉でも雌しべの柱頭につけば受粉も受精も起こり、その結果たくさんの種子が大きな果実の中にできます。温室内でもときどき果実ができます。


開花中の雌しべの下方にある子房(受精後に果実になる)は長さ1~2ミリしかありません。
この小さな子房が、長さ15センチほど(大きなものでは長さ30センチ)の大きな果実になるとは驚きです。自生地や栽培地では、カカオの送粉は、主にハエの一種である「ヌカカ」やアリによって行われます。子房の基部に蜜を出す蜜腺があるらしく、それがハエやアリのねらいのようです。
大きな果実には20~60個の種子があり、つくったことはありませんが、全体の種子から板チョコが1枚つくれるそうです。ここからどうやってチョコレートができるのか? 種子には果肉(pulp)と呼んでいる部分があり、(外)種皮が発達したものです。焙煎してチョコレートの粉末にする部分は、受精卵から発達した胚です。ここに栄養(脂肪)がたっぷりと含まれています。ちなみに、カカオの種子散布は、主に鳥やコウモリなどの動物によって行われます。
10月は、秋が進むにつれ、キンモクセイ、シクラメン、ツリフネソウなど、いろいろな花が咲きます。

(キンモクセイ)

(シクラメン)

(ツリフネソウ)
戸部 博 京都府立植物園 園長
1948年青森生まれ。東北大学理学部卒業。千葉大学理学部助手、京都大学理学研究科教授など39年間大学につとめる。その後、日本植物分類学会長、日本植物学会会長などをつとめ、2018年4月1日より京都府立植物園の園長に就任。自らの主導により植物や植物多様性保全、京都府立植物園に関する研究を専門家によって一般の方に分かりやすく伝えるサイエンスレクチャーを2023年より植物園にて開始。
文/戸部 博
【画像】京都府立植物園