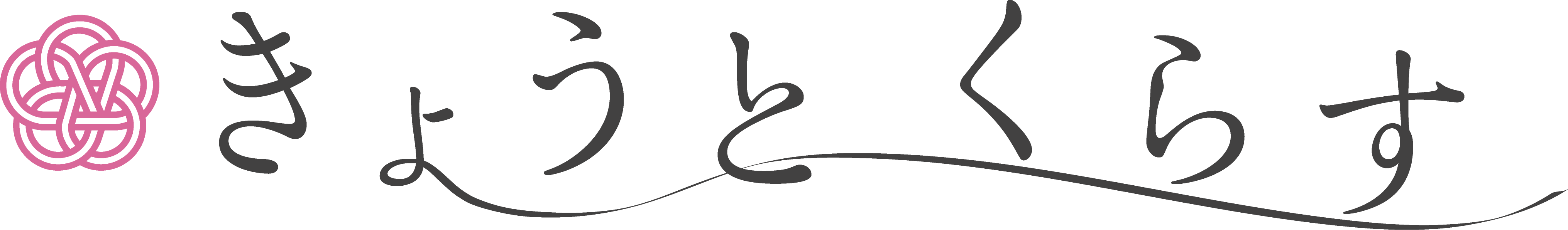祇園白川沿いの風情ある場所にたたずむ料理旅館白梅。老舗の格式、きめ細やかなおもてなしで、国内外から高い評価を得ています。
その人気旅館の女将から見る祇園の景色を『きょうとくらす』で毎月1回、コラムでお届けします。

今回は、京のまちが熱気に包まれる『祇園祭』についてお話しします。
祇園祭の月は…

旅館でお出しするお菓子が厄除けの水無月になる頃、祇園町がソワソワとし始めます。祇園祭がまもなく始まります。
街のシンボル、鎮守の八坂神社の祭礼、日ごろ、スサノオノミコト大御神様のおかげでお商売をさせていただいている私たちにとって、人の多く集まる祇園のまちは、何をおいても神様へのご奉仕を優先すべき場所なのです。
やはり祭りは体力を使い大変ですが、みんな口々に「仕事もあるのにやってられへんわ~」と言いながらも何故か嬉しそう。お祭りには不思議な力がありますね。
祇園祭といっても様々な儀式や祭礼が1ヵ月に渡り続き、準備はというと祇園祭が終わったらまた次の年の準備が始まり、春の桜が散る頃はいろんなところでそれぞれの準備のための会合が開かれます。
華やかな山鉾巡行は祇園祭の見せ場ですが、実は祭りの本番は神輿渡御。3柱の神様であるスサノオノミコト、奥様のクシナダヒメノミコト、その子どもであるヤハシラノミコガミを乗せた3基の神輿が渡御し京都を祓い清めます。
山鉾には、神様がお通りになる道を先に清めるという大切な役割があります。街中はいっぱい鬼や悪いものが集まっているので、山鉾で先に回収して回ります。
巡行のあと、山鉾がすぐに解体されるのは、集められた鬼や邪気が再び逃げ出し、街に散らばってしまわないようにするためだとも言われています。
世代によっての楽しみ方

小学生の頃は夕方八坂神社を出発するお神輿の後をついていくとあちこちでお振る舞いがあり、神輿の担ぎ手さんへはお神酒やビール、子供たちもジュースやお菓子がもらえてそれは楽しかったものです。
ただ、お祭りは楽しいという概念を植え付けられたのもこの頃です。
中学生になると、祇園祭の関心は宵々山、宵山に。「いつも早く帰ってきなさい。」という祖母や母もこの日ばかりは店が忙しいこともあって門限がありませんでした。
さらに高校生になると、誰とお祭りに行くのが重要になってきます。彼のいない女子は友人数人と行くか、もしくは彼女のいない男子グループと合流し気になる相手がいる女子はさて彼に宵々山に誘われるのか、宵山に誘われるのか運命の分かれ目になります。
大人になると今度はだんだんと祭りを支える側になっていきます。感じるのは、
祭りがある街は人と人のつながりが生まれ、循環しているということ。ともに苦労し成し遂げることがあると人は結束し絆が生まれます。それがひいては暮らしやすさ、お商売にもつながっていくのです。
今私はお神輿をお迎え、又見送る際の祝い提灯行列の役をしていますが、これは江戸時代、お神輿をお迎えする奉祝行事として、鳥居形や角樽、将棋の駒屋、鶏形など、お目出たい変わり提灯を掲げた町衆が行列し祇園社へお参りをした行事が明治になって途絶えていましたのを8年前復活させた行事です。はじめは7基だった提灯が8年目の今年は54基にも増え、芸舞妓も行列に加わり、それは壮麗で美しいものです。神輿洗いの7月28日、午後8時ごろから9時半ごろまで祇園を練り歩いています。是非見にいらして下さいね。
さあまた暑い夏が始まりますよ、気張りましょ!
奥田朋子(おくだ ともこ)/料理旅館白梅 女将
1965年京都生まれ。1989年全日本空輸株式会社にCAとして入社。
1997年より若女将として、2017年より女将として料理旅館白梅を経営し、2017年より祇園新橋景観づくり協議会会長として京都、祇園の街づくり活動にも積極的に参加している。
文/奥田朋子
【画像】料理旅館白梅