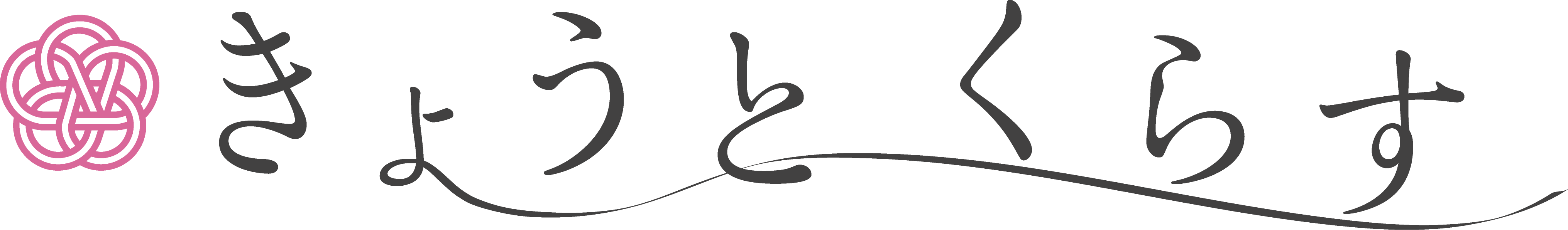2024年で開園100周年を迎えた京都府立植物園。
日本で最初の公立の総合植物園として誕生して以来、府民に親しまれ、歴史を重ねてきました。四季折々の草花の栽培はもちろん、希少な植物の保全にも力を入れています。
このコラムでは、植物の専門家である戸部園長に季節ごとの見どころやユニークな植物の生態を教えてもらいます。物言わぬ植物から学ぶことはたくさん!緑に癒され、潤いある暮らしのヒントも見つけてくださいね。

7月が見頃の植物たち
多くの植物の花は日中開花し、夜間は閉じるか日中の姿のままです。それと対照的に、日中閉じて、夕方暗くなり始めると開花する花をもつ植物もあります。それらは夜行性植物といい、当植物園で昨年開花したショクダイオオコンニャクや、毎年開花する名物バオバブも夜行性です。今から40~50年も前、アフリカや中米で、ある夜行性の植物の花があり、それをネズミが訪れて蜜を吸う一方、花粉を他の花へ運搬していることが発見されました。知られざる植物と動物の世界が明らかになり、大きな話題になったことがありました。

(ショクダイオオコンニャク)
当植物園の観覧温室内にはそうした夜行性植物だけを集めた「昼夜逆転室」と呼ばれる一画があります。来園者が訪れるまだ明るい時間帯にそのエリアだけを暗くして、夜行性の植物を咲かせています。
まず、夜の女王と呼ばれるサボテン科の1種や月下美人があります。

(夜の女王)

(月下美人)
また、ナス科のコダチチョウセンアサガオ、ケチョウセンアサガオ、ブルグマンシア、ニコチアナの1種、さらにアカバナ科のマツヨイグサなどもあります。

(コダチチョウセンアサガオ)

(マツヨイグサ)

(ツキミソウ)
夜行性の花は、たいてい一晩だけ、長くても数晩、短時間だけ咲きます。夜になると開花する植物の種数が世界中でどれぐらいあるのかよく分かりません。しかし、熱帯ほど多く、緯度が高くなるにつれて少なくなります。その理由は、夜間に花を訪れる動物の種類が高緯度ほど少なくなるためです。日中は閉じた状態にある夜行性の植物の花は、夕方になると花弁が開きはじめ、特別な匂いを出して夜行性の昆虫を引き寄せて花粉を運んでもらいます。その見返りの報酬として蜜や花粉を提供します。もちろん、花から発する匂いでも、コウモリが好む匂いと夜行性のチョウやガが好む匂いは違います。そのうえ花の特徴も違います。例えば、コウモリがやってくる花は濃度の濃い蜜を大量に、花粉も大量に出します。そうしないとコウモリが必要とする十分なエネルギーが得られないからです。一方、花は蜜をつくるための大きな蜜腺をつくり、花粉をつくる雄しべは数百本もあります。花はそれらの蜜や花粉をコウモリに奪われるのですが、そのかわり受粉を確実にし、次世代の種子を残すことに成功します。
怪談話に出てくる「草木も眠る丑(うし)三つ時」は午前2時ごろにあたります。本当に植物は眠るのでしょうか? 冬に芽が休眠(冬眠)のことではありません。我々人間と同じように毎朝晩起きたり眠ったりするのかということです。人間は夜になると疲れをとるために休みますが、植物も夜は眠って休みをとっているのでしょうか?答えはNOです。光が与えられれば24時間光合成をし、成長を続けます。そんな植物って、すごいと思いませんか?
戸部 博 京都府立植物園 園長
1948年青森生まれ。東北大学理学部卒業。千葉大学理学部助手、京都大学理学研究科教授など39年間大学につとめる。その後、日本植物分類学会長、日本植物学会会長などをつとめ、2018年4月1日より京都府立植物園の園長に就任。自らの主導により植物や植物多様性保全、京都府立植物園に関する研究を専門家によって一般の方に分かりやすく伝えるサイエンスレクチャーを2023年より植物園にて開始。
文/戸部 博
【画像】京都府立植物園