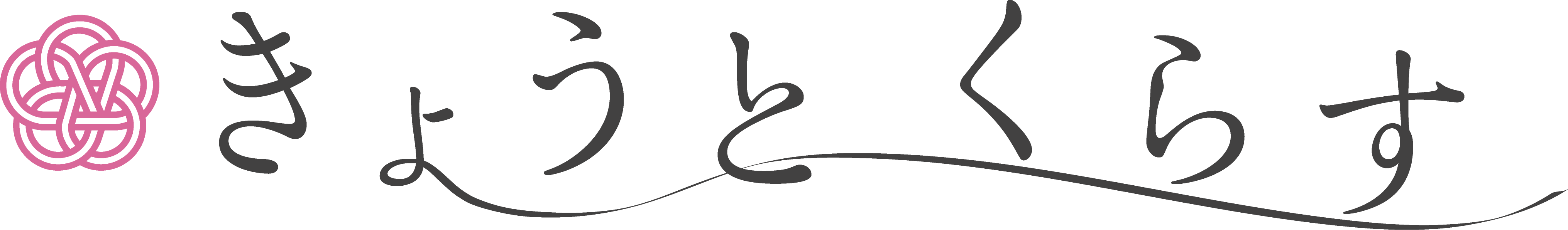2024年で開園100周年を迎えた京都府立植物園。
日本で最初の公立の総合植物園として誕生して以来、府民に親しまれ、歴史を重ねてきました。四季折々の草花の栽培はもちろん、希少な植物の保全にも力を入れています。
このコラムでは、植物の専門家である戸部園長に季節ごとの見どころやユニークな植物の生態を教えてもらいます。物言わぬ植物から学ぶことはたくさん!緑に癒され、潤いある暮らしのヒントも見つけてくださいね。

8月が見頃の植物たち
今夏、植物園では子供たちの夏休みに合わせて「植物と昆虫展」を開催しています。 植物と昆虫のさまざまな深~い関わりのうち、今回はひときわユニークな花と昆虫の世界を紹介しましょう。

植物園の中央に大芝生地があり、その南西の樹林の中にイチジク、イヌビワ、ホソバイヌビワといったクワ科の植物が数本植えられています。イヌビワやホソバイヌビワは日本の野生種で雌雄異株、つまり、雌株と雄株に別れています。植物園内にあるのは雄株だけです。

6月中旬になると長さ1センチぐらい達する隠頭(いんとう)花序(かじょ)と呼ばれる特殊な花序(花の集団)に発達します。

どれぐらい特殊かと言うと、花序はいわば袋(花嚢(かのう)といいます)になっていて、その中に無数の小さな花をつくります。

花には、雄花、雌花、産卵のための虫えい花の3種類があり、雄花は花粉をつくり、雌花は受精後に種子になる子房をつくります。虫えい(虫こぶ)花も子房に似た構造をもっていますが、そこに雌バチが産卵します。
そして7月初め、イヌビワの雄株に大小の花嚢(中に雄花と虫えい花ができる)ができます。イチジクコバチの雌バチが産卵のために、花嚢の先端にある入口を通り抜けて中に入ってきます。その際、雌バチは入口で翅(はね)を落としてしまうため、中に入った雌バチは外に出てくることはできません。 さて、雌バチは虫えい花に受精卵か未受精卵を産卵し、ほぼ球形の虫えいをつくります。受精卵からは雌バチが、未受精卵からは雄バチが孵化し羽化します。ただし、雄バチには翅がありません。成虫になった雌バチは雄バチと交尾して受精卵をつくるか、未受精卵を抱え、大きく開いた出口から外へ飛び出していきます。

その際、雌バチは、やや遅れて花嚢の出口付近に発達した雄花の花粉を集めて出て行きます。もちろん翅のない雄バチは花嚢の中に残り、やがて死んでしまいます。
飛び出した雌バチは再び雄株の花嚢か、あるいは雌株の花嚢に侵入します。雌株の花嚢に入った雌バチは、前述のように虫えい花に産卵する一方、運んできた花粉を雌花につけて授粉し、雌花はやがて種子をつくります。
このようにイヌビワの花嚢はイヌビワコバチの産卵のために欠かせません。一方、イヌビワもまた種子をつくるためにイヌビワコバチが欠かせません。両者は相利共生と呼ばれる特殊な関係を持ちながら生き続けています。飛んで移動するのは雌バチだけ(花嚢から花嚢へ1回だけ)で、一方、雄バチは花嚢の中で交尾のためだけに生きていて一生外に出ることはありません。面白いと思いませんか?

花が少ない季節ですが、サルスベリ、ハマゴウ、ヒオウギ、ムクゲ、ハス、オニバス、レンゲショウマなどを楽しめます。
戸部 博 京都府立植物園 園長
1948年青森生まれ。東北大学理学部卒業。千葉大学理学部助手、京都大学理学研究科教授など39年間大学につとめる。その後、日本植物分類学会長、日本植物学会会長などをつとめ、2018年4月1日より京都府立植物園の園長に就任。自らの主導により植物や植物多様性保全、京都府立植物園に関する研究を専門家によって一般の方に分かりやすく伝えるサイエンスレクチャーを2023年より植物園にて開始。
文/戸部 博
【画像】京都府立植物園