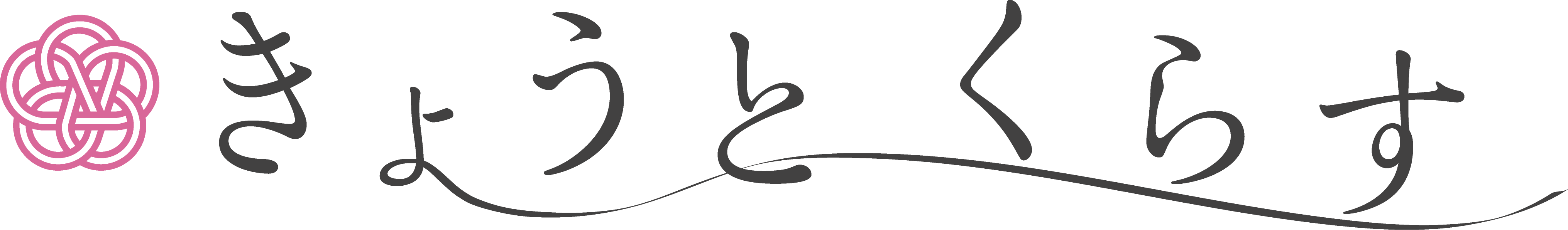2024年で開園100周年を迎えた京都府立植物園。
日本で最初の公立の総合植物園として誕生して以来、府民に親しまれ、歴史を重ねてきました。四季折々の草花の栽培はもちろん、希少な植物の保全にも力を入れています。
このコラムでは、植物の専門家である戸部園長に季節ごとの見どころやユニークな植物の生態を教えてもらいます。物言わぬ植物から学ぶことはたくさん!緑に癒され、潤いある暮らしのヒントも見つけてくださいね。

3月が見頃の植物たち
今年は寒い日が続き、植物園内に雪が見られる日も何度かありました。
そんな寒さが続いたせいか、ウメは開花遅れサクラも例年より遅れそうです。園内には梅林があり、約60品種150本が植栽されています。ウメは古くから親しまれ、7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された、現存する我が国最古の歌集『万葉集』の中で100首近い歌で詠まれていました。
また、ウメは学名で“Prunus mume”と呼ばれています。江戸時代も終わりに近づいた1823年に来日したドイツ人のシーボルトがオランダ商館長の侍医を務めながら、植物の押し葉標本を作り、帰国時に日本から持ち帰っています。彼の耳に聞こえた名前が“ウメ”ではなく“mume”でした。日本で呼ばれる呼称をそのまま学名に使って1836年に発表しています。

さて、ウメとサクラは何が違うのでしょう?
どちらも分類学的に同じバラ科スモモ属(あるいはサクラ属)に属し、DNAを使った比較研究でも両者はとても近い関係にあります。
そのため似ていても当然ですが、中でも5枚の花弁やたくさんの雄しべに囲まれた1本の雌しべなど、花の様子はとてもよく似ています。植物図鑑では、ウメの果実(実)には縦に浅い溝があり、サクラの果実にはそれが無い、という点で識別されています。
それだけでは果実が無いと区別できません。花が咲いているときには区別できないかというと、可能です。ウメの花はふつう枝に1個ずつ咲きますが、サクラは少なくとも3個ぐらいが花序(花の集まり)をつくって咲いています。最近の研究によれば、ウメやサクラの仲間の祖先は、もともとたくさんの花からなる花序をもっていたことが分かっています。進化の過程で、サクラでは花の数がまだ3個ぐらい残った花序ですが、ウメでは1花に減っています。ウメやサクラの遠い仲間のウワミズザクラ、イヌザクラ、バクチノキでも、花序のかたちは違いますが1花に減っています。

サクラは、植物園内に180品種500本が植えられています。国内に自生する種は9種ですが、そのうち7種が園内で見られます。良く知られるソメイヨシノは、原種のエドヒガンとオオシマザクラの雑種です。この雑種が元親のエドヒガンやオオシマザクラと交配してできたものも含めてソメイヨシノと呼んでいます。そのためエドヒガンに似たソメイヨシノ、オオシマザクラに似たソメイヨシノもあり、ソメイヨシノは変異が大きいという特色があります。

京都府の花を知っていますか? 枝垂れ桜(しだれザクラ)です、イトザクラとも呼ばれます。植物園では大芝生地の北にある『はなしょうぶ園』に枝を伸ばした大きな株があります。原種はエドヒガンで、その中の枝が下垂する型の栽培品種です。
例年より遅い開花かも知れませんが、ちょっと知識をもってサクラを鑑賞すると、いつもより楽しいかも知れません。

戸部 博 京都府立植物園 園長
1948年青森生まれ。東北大学理学部卒業。千葉大学理学部助手、京都大学理学研究科教授など39年間大学につとめる。その後、日本植物分類学会長、日本植物学会会長などをつとめ、2018年4月1日より京都府立植物園の園長に就任。自らの主導により植物や植物多様性保全、京都府立植物園に関する研究を専門家によって一般の方に分かりやすく伝えるサイエンスレクチャーを2023年より植物園にて開始。
文/戸部 博
【画像】京都府立植物園