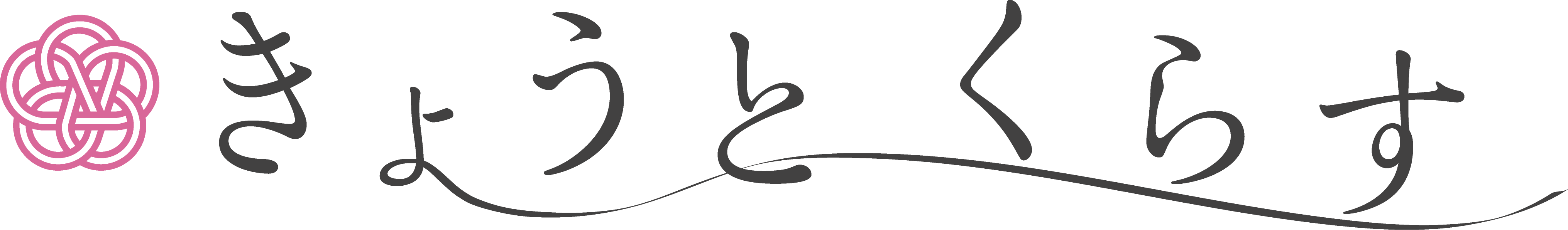「頑張りすぎないマネープランで夢の実現を!」がモットーのCFP(R)認定者(ファイナンシャル・プランナー)・八束和音です。

連載『FP八束の「お金とくらす」』では、子育て世帯が知っておきたい“お金にまつわる知識や情報”をご紹介します。
近年、低年齢の子どもがインターネットを利用したり、スマートフォンを保有したりといったことも珍しくなくなりつつあります。これに伴って、アプリのゲームなどに熱中して、親が知らない間に子どもが勝手に課金をするなどの事例も増えています。
そこで今回は、このような事態を避けるために、気をつけたいことをご紹介します。
スマホ課金の仕組みとリスク

『令和5年度 青少年のインターネット利用環境実態』(こども家庭庁)によると、インターネットを使っている子どもの比率は、2歳で58.8%、4歳で72.1%、6歳で80.9%、7歳で86.3%、8歳で92.3%となっています。小さい頃から、スマートフォンやタブレットでインターネットに慣れ親しんでいることがわかります。
このような状況下で、問題となっているのが“子どもによるスマートフォン課金”。特に、スマートフォンでダウンロードしたアプリを利用している場合は要注意です。親が知らない間に子どもが有料コンテンツを利用して、ゲームのアイテムに大量に課金して請求に青ざめる……といったトラブルも。無料でダウンロードできるものであっても、一定以上のサービスを利用すると有料になるものもあります。スマホ内で、クレジットカードやキャリア決済ができる設定をしている場合には、特に注意が必要です。
親が知らないうちに課金されるパターン

「親が知らないうちに子どもが勝手に課金する」というのはどういった環境で起きるのでしょうか。多いのは、スマートフォンやタブレットにパスワードが保存されていて、子どもが簡単に利用できるケースです。大人が思う以上にスマートフォンの操作に慣れている子どもも少なくありません。また、「有料であることを理解していなかった」という事例も見受けられます。家族で共有のアカウントを利用している時も注意が必要です。
さらに、最近はオンライン上で協力しながら友達と一緒に敵を倒すといったゲームも流行しています。一緒にゲームをしている友達から強いアイテムを手に入れるようリクエストされるといったことも。課金されることがわかっていても、「ゲームに勝ちたい」という欲望に負けてしまう子どもも少なくないようです。
課金を防ぐための方法

このようなスマートフォンの課金は、対策をすることである程度防ぐことができそうです。できることにはしっかりと取り組んでいきたいですね。
パスワードの管理を見直す
パスワードをスマートフォンに記憶させて、使いまわせる状況は避けるようにしましょう。指紋認証や顔認証を利用して、子どもが勝手に利用できないようにするのも有効です。
子どものスマホ利用に制限をかける
スマートフォンには、子どもによる不適切なコンテンツや、購入とダウンロードなどの制限をかけることができる機能もあります。上手に活用してトラブルを防ぐようにしましょう。
プリペイドカードの活用
アプリ内で課金する際に利用できる“プリペイドカード”を活用する方法も。カードには上限額があるため、「その範囲での利用に留める」というルールを子どもと取り決めることで使いすぎを防げます。
FP・八束のひとこと
最も大切なのは「スマートフォンの利用」に関して、あらかじめ子どもとルールを決めておくこと。子どもがスマートフォンやタブレットを使うようになったら、課金などのリスクも伝えておきたいですね。子どもが賢くスマートフォンと付き合えるよう、今のうちからサポートしていきましょう。
関連記事:お金の管理大丈夫? 大学生の家計管理&貯蓄術【FPが解説】文/八束和音(CFP認定者)
【画像】Shutterstock:takayuki/T.TATSU/polkadot_photo