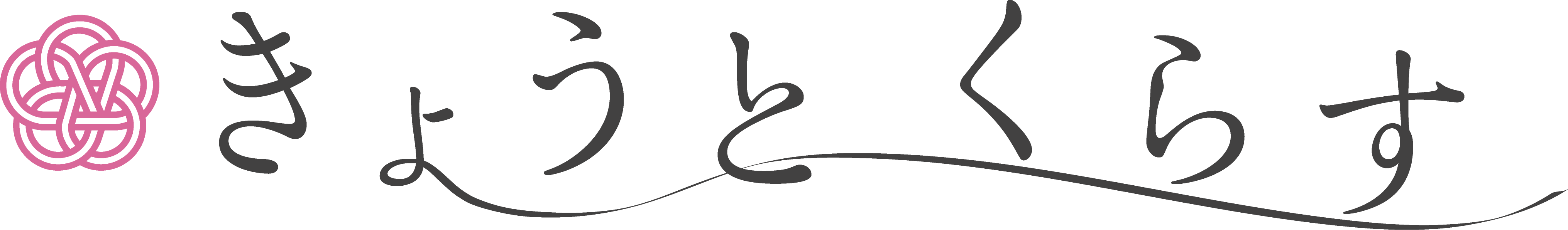9月1日は「防災の日」。いつかやろうと思ってはいるけれど、何から始めたらいいか分からなかったり、子どもを不安にさせてしまうかも……と、つい後回しにしてしまいがちですよね。
でも、もしもの備えは、家族を守るためのもの。
難しく考えずに、まずは子どもと一緒に話すこと、おうちの中を一緒に見てみることからはじめてみませんか? この記事では、京都で暮らす私たちが、今日からできる防災の準備をご紹介します。
【ステップ1】おうちで作戦会議!「もしも」のときのお約束を決めよう

まずは家族みんなで「もしも」のときのルールを話し合いましょう。
「もしも学校や保育園にいるときに大きな地震がきたら、必ずパパかママがお迎えに行くから、先生やお友達と一緒に避難してね」「もしも、おうちが危なくて入れなくなったら、〇〇小学校のグラウンドに集まろうね」など、具体的な場所を決めておく大切さを伝えます。

また、連絡方法のひとつとして、災害用伝言ダイヤル『171』の使い方を、親子で練習してみるのもおすすめです。京都府のサイトにも使い方の記載があるので、この機会にチェックしてみてくださいね。
【ステップ2】おうち探検へ出発!「きけん」を探してみよう

家の中を確認する作業を、子どもが楽しめる「探検ゲーム」に見立ててやってみましょう。
「この大きな棚は、揺れたら倒れてくるかも?」「テレビが飛んでくるかもしれないね」と、危険な箇所を一緒に確認。家具の固定など、大人がすべき対策につなげます。

「地震が来たら、この机の下が“秘密基地”だね!」と、丈夫なテーブルの下など、家の中で避難できそうな場所を見つけておきます。
【ステップ3】わが家だけの「防災リュック」をつくってみよう

非常用持ち出し袋の準備です。「防災リュック」という名前で、自分たちに必要なものを考えてみましょう。
まずは、水や食料、簡易トイレ、ライト、ラジオなど、大人が準備すべき基本のものをリストアップします。

次に、子どもと一緒に必要なものを考えてみましょう。「〇〇ちゃんの好きなお菓子(長期保存できるものを推奨)も入れようか」「不安なときに読む絵本もいいね」と、子ども自身のものを加えることで、「自分のリュック」という意識を持たせます。
【ステップ4】いつもの道が変身!「防災おさんぽ」に出かけてみよう

地域の危険箇所や避難場所を、お散歩しながら確認してみましょう。
「このマーク、見たことあるかな?」と、近所の避難場所の看板を一緒に探してみます。避難マークを認識することで、いざという時に避難場所を見つけやすくなります。

お散歩から帰ったら、「さっき歩いた道は、大雨が降ったらどうなるかな?」と、京都市などが公開しているハザードマップを親子で見てみましょう。これにより、京都特有の河川の氾濫リスクなどにも自然に触れることができます。
編集部のひとこと
毎年9月1日は防災の日。この機会に、いざという時のためにしっかり対策を家族で考えてみましょう。京都府の公式サイトに、防災に関して色々な情報がまとまっているので、ぜひチェックしてくださいね!
関連記事:災害を疑似体験! 親子で訪れたい「防災対策を学べるスポット」【京都市南区】文/きょうとくらす編集部
【画像・参考】 「防災教育のページ」(京都府) (https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/1306133154452.html)を加工して作成
※この記事は情報公開時点の情報です。最新の情報は京都府のHPなどをご確認ください。
※文中の写真はイメージです。